
InterCreation project(インタークリエイション・プロジェクト)から生まれた作品
【Webコンテンツ開発】
プロジェクト発足の経緯
武蔵野大学のキャンパス内に設立された「むさし野文学館」を中核とし、その表現空間をインターネット上へ拡張する公式ホームページ制作の一環として、プロジェクトが立ち上がった。プログラムは2019年9月~2020年1月までの期間で行われ、大学からホームページ制作を請け負うデザイン会社「広告と写真社」のディレクターである井上隆文氏が統括し、大学1~3年の学部生19名が参加して遂行された。
どのように進めたのか
❶ 2019年9月16日 キックオフミーティング
港区東麻布のデザイン会社会議室にてキックオフミーティング。参加者の自己紹介と意欲表明後、今回のテーマである「むさし野文学館Webサイト」プロジェクトの意義や目指すべきゴールについて全員で共有。フリーディスカッションの中から、今回のプロジェクトのターゲットとなるペルソナ(想定顧客の具体像)を設定する。
❷ 2019年10月5日 ブレインストーミング
前回設定したペルソナに届くコンテンツとは何かについてブレインストーミングを実施。コンテンツ制作の素材となる評論家・秋山駿を、どうやって世に知らしめ、ターゲットとなる若者の心を動かせるのかについて議論を重ねる。最終的に「秋山駿キャラクター化計画」というコンセプトが導き出される。
❸ 2019年11月9日 コンセプトメイク
「秋山駿キャラクター化計画」を実行するにあたり、不足している要素を洗い出す。キャラクター化を行うには、プロジェクトメンバー全員が秋山駿の人となりを知るとともに、キャラクターにどのようなセリフを言わせるのかをセレクトする必要があると定義し、各自に著書や資料を読み込み印象に残った言葉をピックアップする課題を課す。同時に、文学評論家としての側面を理解するために秋山駿が選考委員を務めた文学賞(すばる文学賞、野間文芸新人賞、群像長編新人賞、川端康成文学賞)における選評を調査する課題を課した。その課題の成果としてコンテンツ化されたのが、本ページに掲載している「秋山駿語録」と「秋山駿はあの作品に何を感じたのか」である。
❹ 2019年12月7日 コンテンツテーマ決定
学生メンバーの課題提出が計画通りに進まないうえに、参加者数が少なく、次回ミーティングで「秋山駿キャラクター化計画」をフィニッシュできないと判断。急遽参加メンバーと議論を重ねて、「秋山駿とマツコデラックスの相似」をテーマとするコンテンツ制作に方向転換を図る。その成果が、本ページのタイトルであり、下欄に掲載するコンテンツとして結実した。
❺ 2020年1月18日 作品制作&Webプロトタイピング
プロジェクト最終日。前回設定した「秋山駿とマツコ・デラックスの相似」について改めてディスカッションを行い、コンテンツの目指すべきゴールを明確化し、メンバー全員で原稿を制作。さらに、その原稿をWebサイト内のコンテンツとして発信するために「Adobe Photoshop」と「Adobe XD」というデザインツールを駆使してプロトタイピング制作を実施。
▼ このようなプロセスを経て、学生が完成させたコンテンツを以下に掲載します。
秋山駿語録
ここに一つの石塊がある。私がそこを通りかかる。ここの石塊は、何故あるのか。 この石塊は私のためにある、といえようか、否。私が美しいからある、といえようか、否。私がそこを通りかかるそのためにある、といえようか、否。この小さな平凡な石塊とは何か。こんな無意味な自分という存在を、一塊の石ころのように道端に投げ捨ててしまいたい、と思うのだった。
『舗石の思想』より
「私」というのは、すでに何物かではないのか。
一歩を踏み出す毎に、その背後に私の死がある。一歩を踏み出す毎に、そこで私の生が再生する。私は歩く、私の時間を切り開きながら。歩行とともに、私の時間が開かれ、私は私の時間の中を行く。一歩を歩く度毎に、新しい時間のために、この風景の全体が揺らぐ。
われわれが死や犯罪に感動しないのは、その行為の直接さ、意味の明瞭さなどのためであって、われわれが感心するのは、自分が知らぬあいだに犯しているような犯罪の性質であり、ゆっくりと緩慢に少しずつその死を知らせながら死んでいくものの死である。
『歩行者の夢想』より
人の心にも季節がある。
「私」とは、ぽっかりと生に穿たれた底なしの穴、つまり「傷」である。
少年時代は、雑然とした玩具箱に似ている。
言葉は人生を歩くための杖である。というより、心の杖である、といった方がよかろう。若い時は、高く飛ぶための杖だが、老いれば、転ばぬための杖である。
生きるとは、ほとんどの自分の生を疑う行為と同義のものだ。
『片耳の話』より
私は生れつきが病弱だったせいか、生きることは受苦である、というと飾った言葉になるが、すべてを忍耐することだと思っている。人と戦おうと感じたことが、かつて一度もない。私の少年時の生のテーマは、道端の石ころ、であった。それは、打ち棄てられ、黙殺され、人に踏まれて存在する。そういう存在とは何か、と問うたとき、私は初めて生の発光を視た。
人前に出るための服を脱げば、自分がどんなに深くだめな人間であるかを痛く知っている。
『信長発見』より
私が知る主婦は、今がいちばん良い時代だと言う。そう言いながら、病気の老人を抱えて苦しんでいる。それが日本という国さ。福祉の問題を言っているわけではないよ。結局、日本は今も、江戸時代じゃないのだろうかね。
『信長 秀吉 家康』より
ぼくは、人の一生とか、生涯とか人生とかいう、頭のいかれた連中の好むああいうあいまいな言葉が嫌いなのだ。
平和な状態とは、犯罪というこの小さなものが主役を振られる状態である。
平和な状態とは、人の内面を一現実として扱わねばならない時になった、ということでもあるのだ。
「知識」という良いものが、「外国品」という華やかなものより、よりいっそう激しく要求されることがある。(略)なぜなら、華やかなものは、人間の表面を飾るに過ぎないが、良いもののほう─そのある、なしは、人間の内面からその人の生の意味を決定するからである。
「私」とは、私とは何かという疑問のことなのである。
昔は親愛したその人を、三十年も経ってから見返して当時の記憶を新たにしようとしても、
もう昔の親愛の思い出は還ってこない。これは辛い作業である。
『内的な理由』より
石ころが私の友だ。いや、石ころを鏡にしてすべてのものを測ってきた。石ころは、二つに割られても、石ころであり、細かく砕かれても、石ころであり、人に踏まれても、土中に埋められても、石ころである。
私はあまりに生を深く掘り過ぎた。―人と並んで立っていることができぬ。
ああ私を殺せ、私の神!
「私小説」があるように「私哲学」があってよい。むしろ「私哲学」の存在を見過してきたところに現代の陥穽があるのではないか。
いかなる苦痛がこようとも、心は死なぬ。
『日』が主人公であって、『私』が従者である。
私にはもう血も涙もない。しだいにそういう人間になってきたのだ。精神に生きるとは、そういう事なのか。それとも、これは私の歪みなのか。
『「死」を前に書く、ということ「生」の日ばかり』より
秋山駿はあの作品に何を感じたのか。 (文学賞選考委員としてのコメント集)
「京都よ、わが情念のはるかな飛翔を支えよ」松原好之著 (すばる文学賞 第3回(1979年)受賞作)
詮衡の場面をざっと心に描いていくと、予想と現実とは正反対に、がらりと違って進行することがある。というのも私は、『京都よ、わが情念のはるかな飛翔を支えよ』を読んだとき、これは厄介な小説だな、と思った。私は支持することに決めたが、こういう小説は減点方式でしか採点されまい、それでは気の毒なことになるな、と考えた。
読み始ると、冒頭すぐ、「わずかに吹きつけてくる風」なのに「手紙ははたはたと翻り」とある。いったいどういうことになっているのかな、と戸惑う。もう少しいくと、主人公が予備校生として下宿している京都のことを、「こんな地の果て」という。やれやれ、と思う。もう少しいくと、「俺の自閉空間は『関係』の条項を獲取する」などという言葉がある。またやれやれ、と思う。こんなところを減点方式で拾い集めると、マイナスの効果の方が小説より大になってしまうのではないか。そんな気分にさせられる。
そんな減点に、さぞかしうるさいだろうと思われた田久保英夫、黒井千次の二氏が、非常に強くこの作品を支持したので、いま私は安心して悪口を並べている。
私が面白かったのは、そんな減点の部分と裏腹に、というより切っても切れない関係で、小石の光るような記述が点々と存在していることだった。谷川へ岩伝いに登る場面とか、友達との暴力の場面とか。詩も二つくらい、わるくない。そこには、思わず小石を足の裏で踏んづけたときのような、ざらざらした感触があった。まるで樹皮を剥ぐように、およそ抒情味のない単調な青春という果実の断面が、鋭く切開されていた。
明らかに神経症的なタイプの作品である。私にはそこが興味深かった。「光」という言葉のなんという濫用。数学的形容のなんという濫用。明らかにそれは作者の偏執であり、しかしその偏りこそが、迫力をもたらす源になっている。
作者は自分の小さな経験に偏執している。その偏執を「こんな地の果て」というような変換式にかけて、深化しようとしている。私は、作者が思い違いをしなければいいが、と思っている。作者がその変換式で発揮しているのは、情念の飛翔ではない。偏執の核となる自己の感覚への固執である。
私はこの作品に接したとき、なぜか、彼が所持している生のパレットから、本質的に一つの色を欠いている画描きの絵、といったイメージを受けた。一つの色に盲目であるところの画描きが、その不自由に喘ぎながら描いた作品、という感じを受けた。
欠けたその一つの色が、人間化という最後の色でなければいいが。この作品、人間化の色を発揮すべき「葉子先生」の描写では、いやに躓いてしまっているから。
「ギンネム屋敷」又吉栄喜著 (すばる文学賞 第4回(1980年)受賞作)
『ギンネム屋敷』は、候補作中これだけが、いささか小説のでこぼこを持っていて、そのことによって僅かに力を示す、といった制作である。
沖縄の人間の歪んだ皺の部分を描いたものだといっていい。朝鮮人を強請にいくあたりのところが面白い。ただし、この朝鮮人と主人公の関係が、分りにくい。
沖縄の皺々を描こうとして、沢山の細部が持ち込まれる。しかし、要素があまりに盛り沢山に過ぎて、描き切れなかったのではないかと思う。分らないところが多い。戦争中の話や、たぶん昭和二十七、八年頃の時代だと思うが、金銭をめぐる風俗など、私には分りにくい。こちらに知識のないせいもあるが、しかし、説得してくれるだけのふくらみが欲しい。
実は私は、こちらの『ギンネム屋敷』の方に、ちょっと厳しく当った。というのも、私はこの作者に、「文学界」の「九州沖縄賞」の当選の場面で出遭い、その後も時評子として、文芸誌で作品を読んだ覚えがあるからである(以上、銓衡の場では黙っていた。万一に同姓異人ということもあるから)。そういうわけで、素質のある作者なのだから、私は、もっと沖縄の現代を描いてくれ、と要求したい。
「遠雷」立松和平著 (野間文芸新人賞 第2回(1981年)受賞作)
『遠雷』は、このところ安定した実力を見せている立松氏が、力を発揮した一番だが、読後に、もどかしい印象が残った。この作品は、発表のとき、「村雨」と「遠雷」との二つに分けて掲載された。私はそのとき、「村雨」はいいが(前回、この「村雨」の部分が、候補作になった)、「遠雷」の方は、なくもがなの続編と感じた。犯罪の場面や祖母の死による結末のあたり、無用の力こぶである。
ただし、今回は他の四編が、いずれもアメリカを舞台にしたものか、アメリカ的ニュアンスを漂わせるものだったので、近代化による日本の農村家庭の解体を描く立松氏の一編が、反って逆に新鮮なものに見えた。皮肉なものである。
「コインロッカー・ベイビーズ」村上龍著 (野間文芸新人賞 第3回(1981年)受賞作)

講談社文庫
情念の発動
村上龍の『コインロッカー・ベイビーズ』は、この新鋭の力量を証明した作品であると思う。迫力があった。これがあるので、ことしの選考は楽だなと思っていたら、案に相違して、話は紛糾した。
コインロッカーに捨てられた二人の子供の成長物語、迫ってくる都会の悪意とそれに反抗する青年の暴力感覚、あげくの果ての近未来の東京の破壊――こう要約すると、いかにも劇画染みた小説のようだが、そんな図柄を乗り超えて迫ってくるのが、青年達の今日を強烈に生きようとする心情であり感覚である。自分のような者でもどうにかして生きたい、といった背後の感覚の流れているところは、すべて記述が生きている。
この作家には本当に書きたいものがあり、そのために作家としての情念を発動させている、ということが、露骨に伝えられてくる。もっとも、他の委員諸氏には、そこが逆に、情念の空転と見えたのかもしれない。
「家族ゲーム」本間洋平著 (すばる文学賞 第5回(1981年)受賞作)
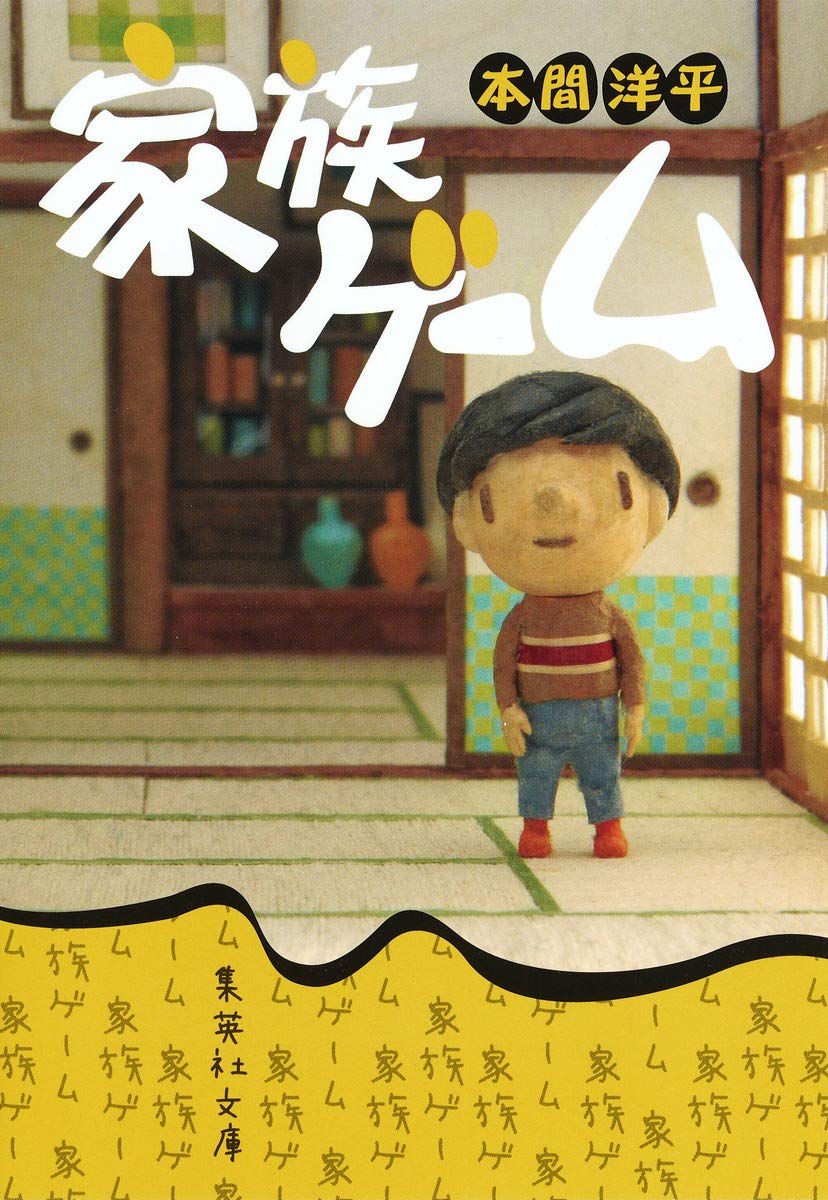
集英社文庫
面白いのはいいが……
みんなで、小説を面白く作ろうとしているらしい。私小説的なもの、あるいは自然主義的なもの、いわば、単純に日常や生活を考えようとしたもの、そういう作品は何処かへ消えてしまった。
あまりみんながそうなってしまうと、私などは天邪鬼だから、下手でも真実味のある作品が欲しくなってくる。小説が面白いのは結構なことであるが、一面、面白さとは、小説における罪なので、小説の面白さを心掛ける人は、同時に罪つくりの戦慄も伴ってほしい、と思う。罪の味を欠いて面白さに走るとき、小説は、今日的な社会の空気が強制するもの、盛んな消費のための娯楽の一形態に過ぎない産物になってしまう。
今回は、面白いといえばみんな面白い小説だった。ただし、本当に小説の面白い果実が成る、というより、面白さを衣装として狙っているようであった。ここにいる人達は、一応の水準なら、どんどん面白い小説を書いていけそうな気がする。しかし、ただの一作でもいいから真に自分が書きたいもの、書かねばならぬものを持っているのか、否か、そういう疑いの前では、みんな心許無い気もする。
私が『家族ゲーム』を推したのは、そんな気分の上に立ってである。これだけが、面白さだけでは割り切れぬ余りの部分を持っていた。この小説の表通りを流れるのは、中学生高校生の受験戦争である。そこへ異色の家庭教師がやってきてドタバタ騒わぎが始まる。小説の表通りは、このドタバタ騒わぎを追って、面白さに走る。
しかし私は、むしろ、そこを買わない。この家庭教師は類型的である。それより私が面白く感じたのは、小説視点者である高校生の、団地の窓越しに見る光景や、本の万引きの心理である。いや、それらの挿話は、小説の表通りとは関係がないために、光景とか心理というほどに、描かれてはいない。空白が多い。
私が興味を感じたのは、実は、そのチグハグな書き方、小説上のアンバランスにある。世間を見るこの小説のレンズは、微妙に歪んでいる。なんとなく不自然なものがある。その微妙な歪みに私は期待した。そしてとにかく、ここには、生活のディティルがあった。
『スクラップ・ストーリー』も、才気のある小説だ、と私は感じた。トランプのカードのように、小説的断片を並べていく、これから流行しそうなスタイルのものである。だが、こんなスタイルを採用するのなら、断片の中身が、もっと工夫されてもよかった。
これでは、ごく普通の若者小説をスタイルで飾ってみただけ、ということになってしまう。気の利いた科白を思いつくのは、案外に楽な作業である。もっと平凡なものがそのまま光ってくるような断片の切れ味、といったものが必要だろう。
『ボクサー』の冒頭、青年が吉祥寺辺の飲み屋で、いかに巧妙に、いかに狡猾に少しでも多く呑もうかと、うろつく光景は、思わず微笑したくなるほど、感じの出ている記述だった。それはいいのだが、後半、青年が女を犯すために公園に行くところが、意外につまらなかった。一見、面白そうな図柄なのだが、こういうところで反って小説が小さくなってくる。
「さようならギャングたち」高橋源一郎著 (群像長編新人賞 第3回(1981年)受賞作)
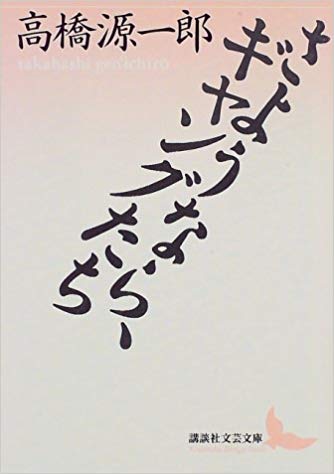
講談社文芸文庫
魅力あれば、傷深し
また、新しい経験をしたように思った。
こういう新人作品選考の場では、傷も深いがそれだけ魅力も深い作品を、と望むのが、まあふつうの心理である。ところが、今回、それが短篇だけに通用する心理であることに気がついた。長篇には当てはまらない。
思ってみれば、意外なことでもなんでもなかった。長篇は、その構造から発して、魅力とともに傷を共存させているものであろうから。山があれば、谷があるに決まっている。そして、新人の長篇となれば、ことにその両極が目立つ。
ことあらためてそんなことを考えたのは、一つの困惑すべき作品――浜谷健司の『蜜柑』に出会ったからである。これは、第一の主題として、男色の行為を描いている。それと不可分の第二の主題として、男が女へと変容していくその変化を描いている。構図は、高校生くらいで同性愛的傾向を深め合った二人の日本人青年が、フランスでそれを売春的に実行し、堕地獄への路をうねうねと辿ってゆく、という筋立てになっている。
こんな主題を、逃げずに、正面から描き切っているところがいい。この長篇を真二つに割っての後半、カルロスという外国人によって主人公が女にされていくあたりの記述には、迫力がある。色も香もある小説の果実が形成されている。
が、困惑は、そこから始まる。これに比較しての前半は、退屈であり、傷が目立ち過ぎる。跳躍を目指しての長過ぎる助走、ともいえない。思わず冗談だが、後半だけを千切って、本誌の別の新人賞候補作にしてみたら、と提案したくらいである。この作品は、横顔に痣のある美人のようなものだ。眼向えて見送らざるを得ぬとき、なにか残念な心持ちがした。
高橋源一郎の『さようなら、ギャングたち』も、なかなか面白い作品だった。自由に、思いつきのままに、小説的断片を並べてゆくもので、これはこれから流行しそうなスタイルである。やがては、こんなスタイルで、一人の人間の精神と、心理と、感受性との非連続性や、やはり一つの経験としては綜合しがたい外界とのジグザグの関係、といったものが、丸ごと捉えられるようになるのだと思う。
この作者には、才気がある。ただし、その才気はなんというのか、新設の専用道路を新品の自転車で走っているような趣がある。そして、その趣を、作者自身が喜び過ぎている。もっと街中で、疾走や曲乗りを試みてもらいたい。つまりこの作品、思いつきはいいのだが、アイデアが楽に流れ過ぎていて、結果として、一つの晴れやかな青春小説にしかならなかった、という憾みがある。が、いちおう、私はこれを受賞作に推そうとした。
他の二篇にも、長篇にしかあらわれぬ意欲はよく感覚された。が、傷はなお深かった。
「羊をめぐる冒険」村上春樹著 (野間文芸新人賞 第4回(1982年)受賞作)
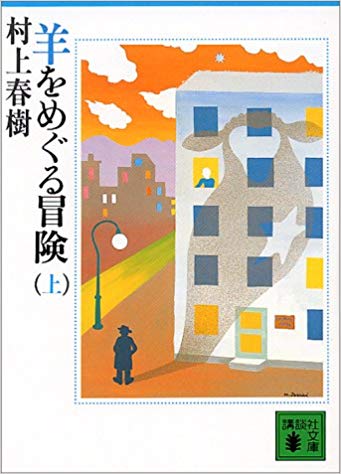
講談社文庫
(c) Illustrated by Maki Sasaki, 1982 /
Medialynx Japan Co., Ltd
今回は作品の粒が揃っている感じで、銓衡に難渋するのではないかと思われたが、そうではなかった。
村上春樹の『羊をめぐる冒険』は、この作者の発案した、気の利いた、しかし時に気障りなところもある話法を存分に駆使したもので、とにかく面白かった。一匹の霊能者の羊を捜しに出掛ける旅を中心に、物語が成立している。こんな話法のスタイルでも長篇が描ける、というところが目新しかった。作者が自分の小説の世界をしっかりと支配している。
「さして重要でない一日」 伊井 直行著 (野間文芸新人賞 第4回(1990年)受賞作)
伊井直行の「さして重要でない一日」。この作家、処女作「草のかんむり」は面白かったが、その後書くものが、いかにも無方向の作家、無方角の作品と見えて、私は首肯しなかった。
しかし、この「さして重要でない一日」は、物の存在より記号性が、現実感より抽象性が、いずれも上位にあるような会社人間の生態を描いてすっきりしていた。あ、これが現代詞の生活なのか、と思わせるものがあった。ディテイルや挿話に、光るものがあった。
「なにもしてない」笙野頼子著 (野間文芸新人賞 第13回(1992年)受賞作)

講談社文庫
今回は、候補作の五篇がみな一つずつ、書き方というか作品のスタイルが違っているので、そのことに興味を覚えた。
笙野氏の「なにもしてない」は、極度に内向的な主人公のモノローグといったもの。ふつうこのタイプの小説は、「ナニモシテイナイ私」という主題を持ち扱かいかねて、つまらぬ観念に堕してしまうことが多いが、これは、「三倍程にも膨れた手の指」を中心に、生理的にはっきり描いてくれるのがよかった。作家の資質ということが、露骨に感ぜられる。ただし、こういう主人公は、自分の部屋にいるときが光っているので、新幹線に乗って動き出すと、影が薄くなる。前半の密度と鮮かさが持ち堪えられていない。
「くっすん大黒」町田康著 (野間文芸新人賞 第19回(1997年)受賞作)
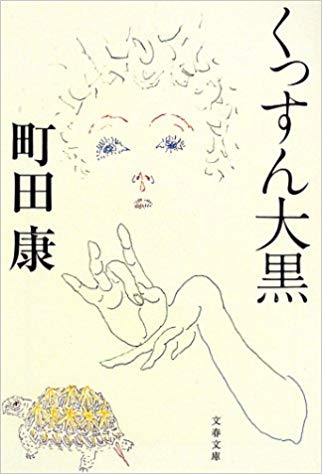
文春文庫
笑いで日常を切る
各作品とも、物語としてはなかなか面白かった。あるいは、面白くする工夫があった。だが、仕掛けに気を取られ過ぎて、その分文章が低く流れるところがあった。
町田康の『くっすん大黒』は、毎日酒を飲んでぶらぶらしていたい男の日常と行状を描く。饒舌体である。二、三ページ読み出したときは、なんだかケレン味の強い話法かなと思ったが、そうではなかった。一本筋が通っている。芯が強い。生きるということが本来備えている批評の力には、一方の極に笑いがあるが、笑いに達するそういう力で、日常というものをしっかりと掴み、切ってみせた。足が地に着いた饒舌で、思わず共感の笑いを発するところがあった。
「おしゃべり怪談」藤野千夜著 (野間文芸新人賞 第20回(1999年)受賞作)
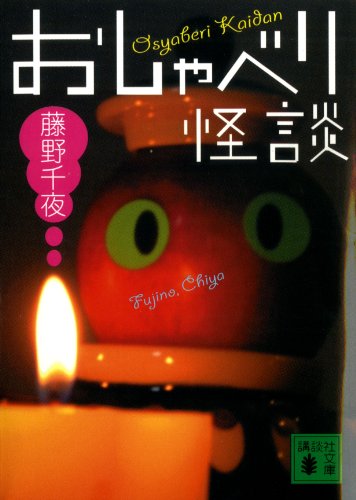
講談社文庫
藤野千夜『おしゃべり怪談』は、表題作がおもしろかった。女四人が麻雀屋へ行く。すると店主を刺した男が侵入してきて占拠される。人質になった女達は、えんえんと麻雀を続けることを命令される。こんな情況の雰囲気を、かなりよく描いていた。
私は、以前あった猟銃人質事件を想い出し、小説は、ああいう事件の本体には迫りにくいが、この作者の軽みのある話法なら、雰囲気の何パーセントかは捉えられる気がした。
「ロック母」角田光代著 (川端康成文学賞 第32回(2006年)受賞作)

講談社文庫
今日的な生の気分
これといって何ということもない日常、事件めいたものが一つもない日常を描いて、作品を結実させることが、今日ではむつかしいことらしい。
角田光代さんの「ロック母」が、よくそんなことを果たしていた。
二十代後半の女性が、十年ばかり東京暮らしのあげく、生まれ故郷の島へ戻って、父無し子を産む話であるが、別にドラマめいたものがあるわけでもない。
「赤ん坊の名前もまだ決められずにいるし、産んでからどうするのかもまったくわからなかった。東京に戻るのか、仕事をさがすのか、それともここで父と母に手伝ってもらいながら子どもを育てるのか、またもや私はなんにも決めずぐずぐずと迷い、そうしているうちに、重要なことはどんどん決められてしまうんだろう。」
こんな思いというか声が、作品の全体を覆っている。なんだか今日的な生の気分をよく捉えている、という気がする。この今日的な気分を、批評用語なら何と言ったらよいのか、わたしはうまく思い付かない。
このごろ女性作家が、既製の批評用語の通用しない生の気分を、よく小説化している。そのことをわたしは興味深く感ずる。
「場所」瀬戸内 寂聴著 (野間文芸新人賞 第54回(2002年)受賞作)

新潮文庫
記憶と時間
人は歳をとるとやがて、お前はどうやって生きてきたのか、お前は何をしてきたのか、という問いに、晒されるはずである。
瀬戸内さんの『場所』は、そんな意味の、自分がどんなふうに生きてきたかという生の記録である。私小説であるといってもよろしい。しかし、それに沿って、もう一つ微妙な旋律が流れる。
生の記録の結節点を、自分が棲んだところ、折り折りの暮らしの場所に索めた。それは「記憶」の奥を尋ねる旅であった。記憶の奥に深く分け入ることによって、記憶を通して、自分の内面にあるものを探求しようとする行為であった。
もう一つの旅があった。それは「時間」である。出家されるまでの半生、男女の葛藤のあった半生を、今日、振り返えり見れば、棲んだ場所より重く存在しているのは、二十年三十年と過ぎた時間であった。
時間の旅は、完らぬ。その時間は、彼方へ、未来へと延びてゆく、流れてゆくものだからだ。
過去への記憶と、彼方へと流れる時間。生の二つのベクトルの交鎖点に起って、この作品は書かれている。そこから、誰もが聴かねばならぬ、「私は何者だろう?私はどんな人間だったろう?」という、微妙な旋律が流れ出す。
ひどく素直に書かれているので、読後、人生無常の哀感が発する。
「タタド」小池昌代著 (川端康成文学賞 第33回(2007年)受賞作)
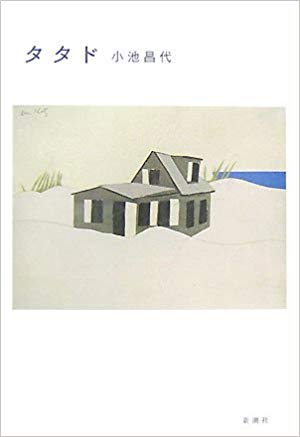
講談社文庫
言葉の強さ
ふと気がつくとこの頃は、一人の人間(主人公)がもう一人の人間(他者)と出合って、小説的ドラマが始まる、という物語は飽きられたらしい。
それとは代わって、自分の思いだけの世界の中へ、死者の声、異生物、あるいはペット的な小動物を、生きた人間みたいに登場させて、思いの内面を深化させるとともに、未知あるいは他界と交流する、そんな作品が目立つようになった。今日的な生の気分の反映か。
小池昌代さんの「タタド」は、お互いに知っているごくふつうの四人の男女が、海辺の家に集うという筋立てなので、これでどんな小説的ドラマが始まるのか、かすかに疑いながらも、気分よく読み出した。
人物一人ずつの登場の仕方、一人ずつの個性が、ごく自然に鮮やかに描かれているので、作者の案内に従い小説の布にくるまれて運ばれる、そんな気分を味わった。
小説的ドラマは、思いも寄らぬかたちで有った。物語の終わりは、四人のスワッピングめいた光景に到る。わざとらしさはなく、作品がしだいに高潮してきてそこへ到る。小説の全体が一つの未知へと浮揚した。
高潮を支えたのは、かかとのひびわれと崇高とを直結させて、不自然を感じさせない、言葉の強さというか文章の力にあった。
「犬とハモニカ」江國香織著 (川端康成文学賞 第38回(2012年)受賞作)
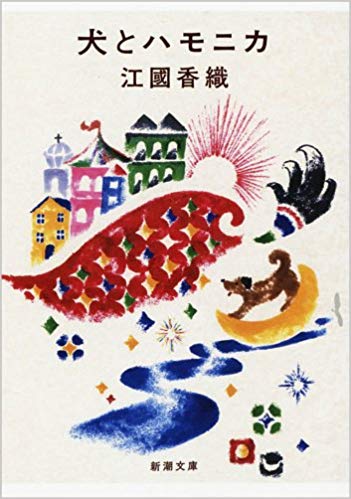
新潮文庫
目には見えないドラマ
江國香織「犬とハモニカ」は、旅客が到着する空港が舞台である。人々は、入国審査の行列に集まっては散り、また、荷物受け取り場に集まっては散る。
この、集まっては散る人の流れの中に、一瞬、渦のように、目には見えないドラマが生ずる。そのドラマが、たいへん良く描かれているので、わたしは読んだあと、大きな道の交差点や、駅のホームを見下ろす場所に立つと、ここにもそんなドラマがあるのかな、と、ふとこの小説を思い出すようになった。
ドラマを描くのは、むろん、作者の手だ。その手は、――夜の天空に無数に散らばる星を眺めて、星座を描き、いろいろ神話的な物語りを古代の人が想像した、そこへ、細い一本の糸で繋がっている。
登場する旅客の誰もが、ちゃんと日常生活の匂いを持って、しっかりと描かれている。なかでも、寿美子という白髪の老婦人と、花音(かおん)という七歳の女の子が、印象的だった。年をとってよかったと思えるのは、他人に頼みごとをしやすくなったことだ、とか、他人をじっと見てもいいのは、子供だけではないだろうか、とか、思わず、なるほどとうなずかせるような個性を持つ。
物語りの隠れたリード役に、アリルドという外国人を振ったのも、好かった。おかげで、ドラマが、日常の外へうまく消えてゆく。
マツコデラックスと秋山駿 時代を超えた相似の正体。
■マツコデラックスから見る秋山駿の必要性
秋山駿とは人々に愛された人である。多くの人を厳しくも暖かい言葉で導き、文学界の空気に流されることなく自分の意見を持って活動していた。マイノリティ、マジョリティに関係なく自身の良いと思う事を良いと言える魅力がある人物だ。
一方で彼は自身の存在にネガティブなイメージを持っていた。その発端は生まれつきの病弱さにあったらしい。少年時代から生のテーマとして石ころを選択するところからもそのネガティブさは窺える。今回の企画において、現代に秋山駿を復活させ、多くの人に知ってもらうにはどうすれば良いのかという議題になった際、やはり今の人々に馴染み深い存在に例えるのが良いだろうという事で、秋山駿に繋がるものがある人物を探した。その結果現れたのがマツコデラックスである。両者共に自分の意見を持ち、素直に発言していること、厳しい言葉のなかにも優しさがあり、多くの人に支持されているにも関わらず自身にネガティブなイメージを持っていること、などの共通点が発見された。マツコさんは今、誰もが知っている存在であり、各メディアにおいて見ない日は無いといって良いほど引っ張りだこで多くの人に求められている人物である。
残念ながら秋山駿という人物は、現在一般の知名度はそれほど高くない。しかし、マツコデラックスが現在求められているように、彼(彼女)と似た性質を持つ秋山駿はこの現代において必要とされる存在であるはずだ。多くの人が秋山駿を知ってくれれば、その中で秋山駿を知ったことにより救われる人も出てくるかも知れない。そのためにも、マツコさんを通して秋山駿という人物に関心を持ってもらいたい。
(藤島駿介)
■なぜ秋山駿とマツコは聞き上手なのか
秋山駿のコンテンツ作成に学生の視点で携わるとなった時、芸能人との共通点を探し始めた。
秋山駿とマツコデラックスの共通点で私が特に関心を持ったのは、聞き上手であり話させ上手であること、個人の意見を物怖じせず発言できることである。他の意見を聞き出せるから自身の知識が深まり、個人の意見を持てるのではないだろうか。
この2人に「マイノリティ」について聞いたらどんな答えが返ってくるだろう。どちらも何かしらのマイノリティに属する者として考えることはあるはずである。世間の目を気にしすぎない率直な言葉で、多様性を目指しても届いてない現代社会を切ったら、我々のうちに秘められた気持ちを代弁してくれるに違いない。
強く優しい芯を持っているからこそ物怖じせず誰も傷つけない発言ができる。博識だからこそ多角的で説得力のある発言ができる。
2人はいつの時代も社会に求められる様な存在だと私は考えた。
(武井春香)
■かっこいい生き方
秋山駿さんとマツコデラックスさんの一番の共通点と感じたのは、お二人とも正しい正しくない関係なく自分の考えをはっきり言っているということである。しかし、好き勝手に言いたいことを言っているという訳でなく、その対象となる人や物事をしっかりと理解し受け止めているという印象を受ける。ひとつひとつ、全てのことに対して関心をもって接している。これにより、発言に対しての信頼が生まれているように感じる。さらに、どちらも「毒舌」と言われる存在だけれども、マイナスなことを並べるだけでなくその対象の良いところもしっかりと見ている。その対象への敬意と礼儀を怠っていない。このように、物事をしっかりと受け止め、相手への敬意を忘れないところが、お二人が愛される一番の理由だと思う。
また、お二人がそれぞれコンプレックスとなり得るものを武器としている点に強みを感じた。秋山氏は自分を「石ころ」と表現して、自身の存在意義について語っており、マツコさんは、体型であったり性的な部分であったり、世間的にマイノリティと考えられるところを隠さずに多くの人に見られる立場に立っている。マイノリティであることを恐れずに、ありのままの「自分」をさらけ出している。このことにより、マジョリティに埋もれて苦しんでいる、お二人と同じようにコンプレックスを抱えている人たちへの道を切り開いているように感じる。
総じて感じたことは、お二人とも「かっこいい生き方」をしているということである。相手への敬意と関心を忘れず、自分の弱みとなりうることを堂々と強みに変えている。これは、人として尊敬できる点だと思う。また、お二人は否定されることを全く恐れていないように感じる。私は、自分が間違ったことを言ってしまうのではないかと不安になり、自分の発言に自信が持てない。お二人からすると、「間違っていること」などは存在せず、全く関係のないことなのかもしれない。もしお二人にお会いしてお話できることがあったとしたら、私はお二人に生きていく上で大切にしていることを聞きたい。私がこれから生きていく中で、自分に自信が持てるようになるためのアドバイスをいただきたいと思った。
今回、私は物事の見方や捉え方を学べたと思う。秋山氏とマツコさんが愛される理由を考えたことで、これからどのようなことを意識して生きていきたいのかということを考えることができた。私もお二人のように「かっこいい生き方」ができるようにしたい。
(小林慶香)
■聞き手に寄り添う
現代を生きる人々は皆何らかの形でSNSを利用しているだろう。SNSでの発言はすぐに拡散されるし、自分の見ていないところで何を言われるかわからないという不安がある。アカウントを非公開にしてしまえばいいかもしれないが、それは自分の意見を閉じ込めていると言えるのかもしれない。そんな現代で、メディアで包み隠さず自分をさらけ出して語るマツコに無意識に惹かれるのではないか。
マツコがこうすることができるのは巧みな会話術があるからだろう。マツコの物言いは真っすぐで正直だが、決して堅苦しかったり批判的なのではなく、茶化しているような感じがする。毒舌のなかのユーモアさがあるから、マツコの言うことに共感できてもできなくても、笑いに昇華できる。意見というよりもっとラフな 、「友達と話している感覚」のようなものをマツコの喋りには感じるのだ。
秋山駿が彼の教えた学生らに好かれたのも、この親しみやすい正直さがあったからなのではないかと思う。聞き手に寄り添う話し方、それが秋山駿とマツコ、二人の魅力のひとつと言えるだろう。
(西野文香)
■愛される二人の共通点
マツコデラックスさんと秋山駿さんの共通点は相手を思いやる態度であると感じた。
マツコデラックスさんは人の話を聞くときに否定から入るのではなく必ず相手の意見を聞いてから自分の意見を伝え、良いと感じた部分は素直に言葉で表現している。
このときの彼女の意見というのは大衆の意見ではなくあくまで彼女自身の言葉である。
立場など関係なくただひたすらに彼女自身が感じたことの言葉であるから相手を傷つけることなく意見を言えるのではないだろうか。
また、彼女は感謝の言葉を口にしている回数が多いと感じる。どんなに小さいことでも人からしてもらったことには感謝を伝えている。人として当たり前のことだが当たり前のことを公の場でしているということも大勢の人が彼女を信頼することができる理由なのではないだろうか。
対して秋山駿さんは批評家であるためときには否定を使うこともある。
しかし否定の部分からは相手を必要以上に傷つけないという配慮を感じることができる。
自分が良いと思ったことは素直に褒め、否定するときは自分はこう思ったという立場を取り大衆の意見ではないことを明確にしている。このことにより批評相手を必要以上に傷つけていない。
二人は決して人を必要以上に人を否定せず相手を尊重し自分の意見を話す。そこには相手を思いやる態度が強く反映されている。だからこそ多くの人に信頼され尊敬されるのではないだろうか。
(関口澪璃)
■マツコさんと秋山先生 二つの 「力」
私はマツコデラックスさんと秋山駿先生には大きく二つの共通している「力」があると考えている。
マツコさんの魅力の一つとして欠かせないのが、相手の意見を否定せずに、まずは肯定し受け止めるという点が挙げられる。秋山先生も同じく、自身を論破しようと挑戦してくる教室の生徒の意見を容赦無く仲裁することはあれど完全に否定することは無く、逆に励まし、リベンジする精神を評価している。この「相手の意見を受け入れ、さらに意見を引き出す力」というのは二人に共通していることであり、人々に受け入れられやすい素晴らしい長所であると考える。
また、マツコさんはバーやテレビでの経験、秋山先生は評論や生徒との会話の中で自分の経験を増やし、分からないことは調べたからこそ豊富な知識を増やした。この「人との対話を自分の強さにする力」という点も共通している。
(田辺慶太朗)
■自己を貫くこと
文学館は評論家の秋山氏から寄贈された文献が多く残されています。本プロジェクトで私たちが焦点を当てたのは秋山氏と、現在、芸能界で活躍されているマツコデラックスさんの間に見られる共通点です。
女装家であるマツコさんは、自分がマイノリティであることを隠すことなく、メディアに登場され、様々な人との対談の中で堂々と自分らしさをさらけ出している様子が、人気を博しています。
秋山氏も評論活動の中で、周囲の意見に左右されることなく自身の意見をしっかりと主張する人物でありました。
多数派にとらわれず、自己を貫き通すという生き方はどれほど困難なことでしょうか。
秋山氏は文芸評論家として作家と実際に対面し、取材をする機会が多かったでしょう。マツコさんは雑誌の編集や、タレント活動の中で、様々な人と出会い、お話しすることがあると思います。
自身と意見や価値観の違う人々と接する中で、秋山氏とマツコさんは彼らの意見に流されるのではなく、より一層自身の意志を強固なものへと変化させていったのかもしれません。
二人に共通する点は、一言で表すと「優しさ」です。人と接する時、マツコさんは相手の話を聞くことから対話を始めます。相手の意見を聞いたうえで、自分の直感に基づいたコメントをします。その時にも否定的な言葉はあまり使われません。一見自分が理解できない話にも、その中で自分が良いと思うもの、好きなものを見つけ出し、素直に意見します。秋山氏は評論を行う際、必ず作品を肯定する文章から始まります。評論なので、批判的な意見をすることも必要ですが、その厳しさには必ず優しさが伴っているのです。
自己を貫き通すために最も大切なことは他人を受け入れることだと思います。相手のことを受け入れないかぎり、自身のことを相手に受け入れてもらうことはできません。相手の意見を丁寧に迎え入れるマツコさんと同様に、秋山氏も相手の良さを受け入れ、そのうえで自身の意見を受け入れてもらおうと心掛けていたのでしょう。現在、多様性が重要視されている世界には様々な人々で溢れています。きっと私自身もその多様な人々のうちの一人なのでしょう。現代社会で自己を貫き通して生きる心得は、マツコデラックスさん、そして秋山氏から見つけ出すことができるのです。
(染谷大鷹)
■万人ウケを狙わない二人
世間体を気にして、はっきりと意見を投げてくれる人が少ない現代の世の中で、そのまま人生の教訓になりそうな言葉をくれる人たち。万人ウケを狙っているわけではないのに多くの人に評価されるのは、着飾らない自分の素直な気持ちを表現しているから。
(田中ひかり)
■ありのままの信用性
現代の有名人で秋山駿に似ている人物は誰か。そんな話題になって、挙がった名前はマツコデラックスであった。厳しくも優しくもあるという評価、酒好き、自分の意見を持っているという共通点からである。
私が秋山駿のことを文章で読んで思ったことは、知人の方々はきつい物言いにも優しさがある、文学に真摯に取り組む尊敬できる人物だと言うのに対して、秋山駿は、自分は石ころで、だめな人間であると言う、大きなギャップがあることである。
現代でマツコデラックスが評価される最大の理由は、嘘偽りのない真っ直ぐな発言にあると私は考える。自分の意見を簡単にSNSなどで発言できるようになった現代では、反対に面と向かって飾った言葉ではない率直な意見を言える人物は貴重になっているのではないだろうか。その意見さえ人々がどう受け取るかというのは様々で、信じるか信じないかは別問題だ。しかし、マツコデラックスの発言は人々には自然と受け入れられているように思う。そもそもメディアで女装やオネエなどのマイノリティに分類される人々が受け入れられるようになったのは近年の話である。まだまだ人々の中で何の偏見もないなんてことはとても言えるようにはなっていない。そんな中、自分がマイノリティであることを隠さずにいるという点がマツコデラックスの発言に説得力を持たせているのではないかと考えられる。
秋山駿は右耳が聞こえず、聞こえる方の左耳を傾け、時には議論に熱が入り口調が荒くなることもあったという。周りの人々はそんな秋山駿の文学に熱心に取り組む姿勢に魅力を感じ、慕っていた。しかし同時に、自分のことを優れた人間ではないと、むしろ才能に憧れる節も見受けられるほど、自分をさらけ出している。これはマツコデラックスと同様、自分を偽らない人物であると言える。
現代ではこうしたありのままであるというのが最も人々に真っ直ぐ受け取ってもらえる要素なのだと思う。秋山駿の真っ直ぐ人の話を聞き率直な意見を言える、この在り方は現代において尊重されるべき人柄だと私は考える。
(齊藤夏希)
■私はこう思う
マイノリティという言葉は一見難しそうで特別に感じるが、実は皆が持っているものであると気付いた。全てのマイノリティが受け入れられていない現在でも、マイノリティを体現し、自分とは違う意見を受け入れつつ、本当の自分を偽らないマツコデラックスに、私は大きな憧れを感じる。
また、秋山駿も自分を偽らずに、石ころに自分を照らし合わせて、平凡さと等身大の感覚を大切にしていた。はっきりと述べる意見の中に、しっかりと愛情が込められている。このことから相手の意見を受け入れられる強さを感じる。
なかなか自分を偽らずに生きていくことができず、ストレスを感じることが多い現代だが、「私はこう思う。」と本当の自分を隠さずに生きた秋山駿のことばは現代の多くの人に響くと思う。
(西田朝香)
■等身大であることの魅力
私の考える秋山駿とマツコデラックスの共通点とは、等身大であることです。自分の理解ができない範囲は否定することもなく「わからない」と伝える、素敵だと思ったことは少数意見だとしても伝える。こういった、大衆に流されずにはっきりと思いを伝える芯の強さが、言葉を受け取る側にとって安心感や信頼感につながっているように思えます。加えて、このお二方は言葉遣いの丁寧さや謙虚な姿勢を根底にしっかりと持っています。そのため、ストレートな言葉を使っていても、不遜さや嫌悪感を覚えにくいというのが、両者の大きな魅力なのではないでしょうか。
(小林弥生)